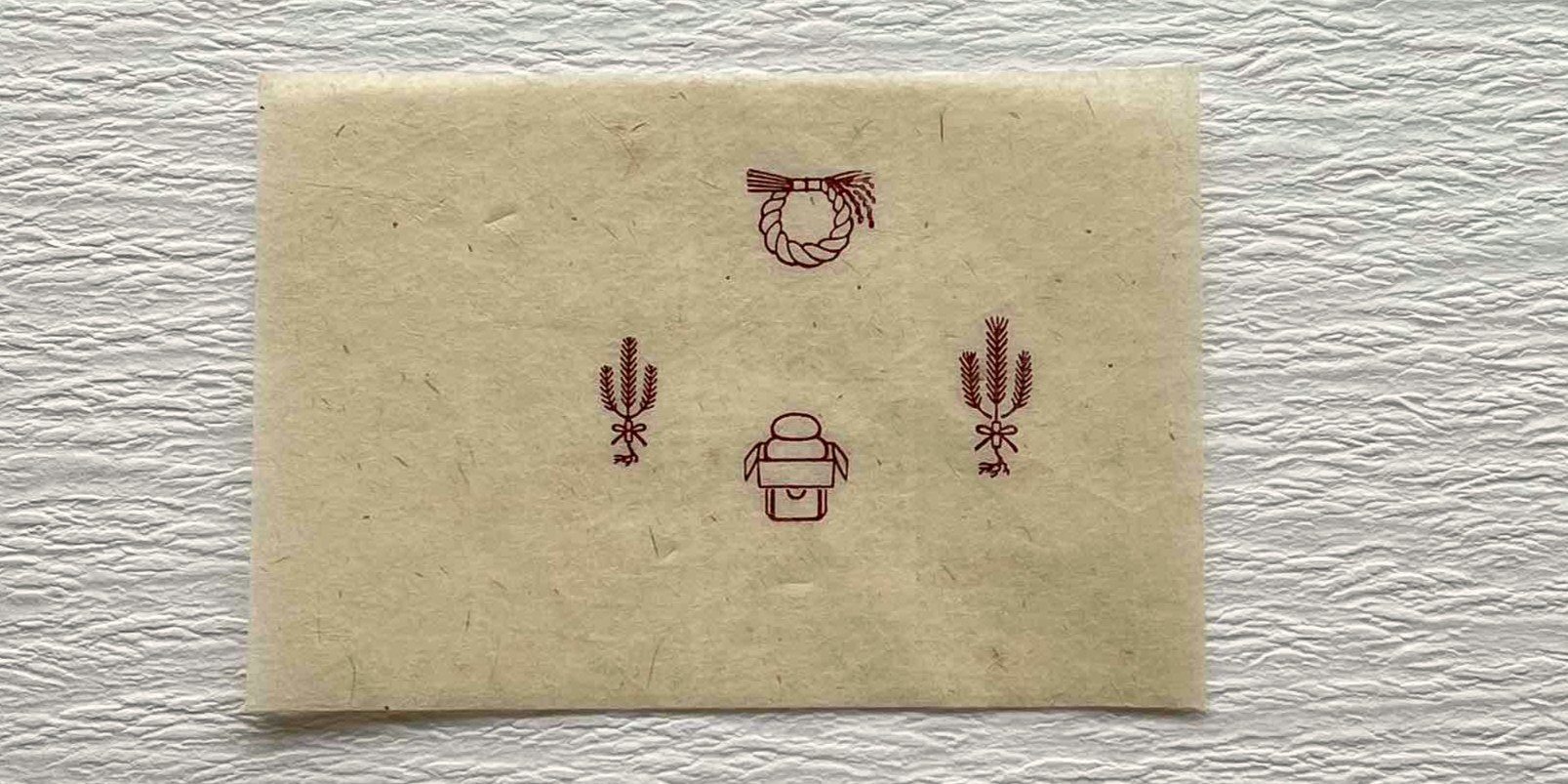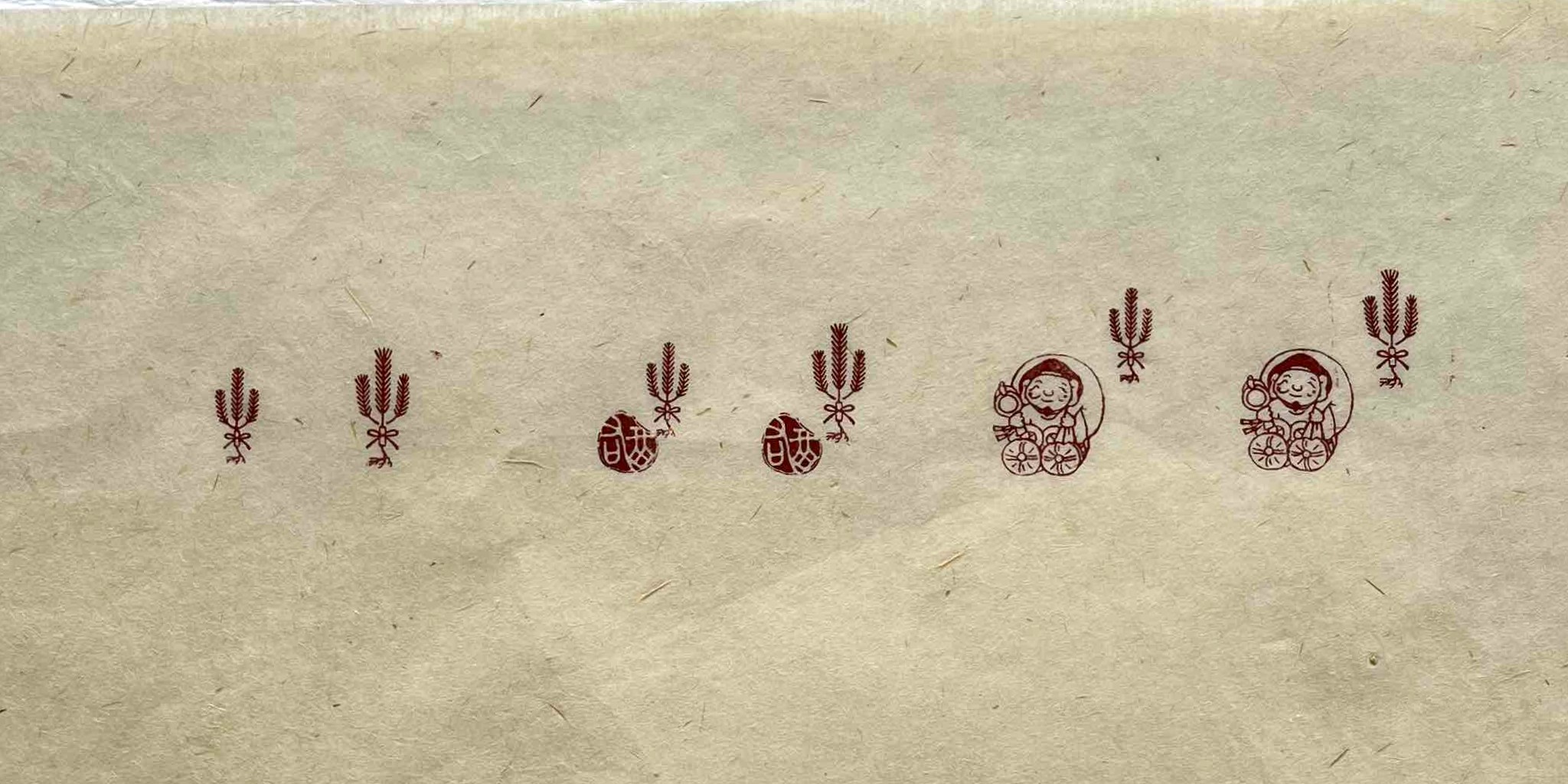松飾りの遊印

初回の試彫。印面サイズ15ミリ角。
こんなに綺麗に彫刻できるなんて!と思わず彫刻機を撫でる。
ROCAdesignの濵田さんにお願いしたのは、
根っこがついた雄松で
根元に白い紙を巻き、
水引はもろなわ結びになっているもの。
たくさんのパターンをデザインして下さって、
その中で直感で気に入ったひとつをまずは彫刻してみた。
縦長になるのは最初からわかっていたので、
正方の印面にはかなり厳しい事になるのだけれど、
私の中では。。。
お正月の大切な三つの要素である為どうしても作りたかった。
この松飾りは今は門松という形で、
家の外、例えば門柱のあたりに二本一対で設えることが多い。
(もちろん今も画像のような素朴な松飾りを雌松と一対で飾る地域もある。)
門松であっても一対のそれぞれは微妙な違い(意味)を含んでいて、
同じものを左右に置いているわけではない。
けれどずっと昔、
江戸時代より前は一対ではなく一本だったと習ったことがあって、
その時は雄松も雌松もない。
松の枝を山(の神様)からもらってきて家の前に立てて目印にした。
その時は根っこはついていたんだろうか?
あるいは根曳きの松を売りに来る行商人がいたのかもしれない。
根っこはついていてもいなくてもよい。
と書かれた本はけっこうあるが、
その起源や意味は私が辿り着けた範囲では曖昧なものが多かった。
ここに歳神様をお迎えする準備ができた家がありますというしるしが松飾りで、そこに降りてこられた歳の神様は結界であるしめ縄をくぐって家の中に入られ、鏡餅の中に宿る。
お正月の間は家の中にいてくれて、その間は神様と人が共に食べ(共食)、
お正月が終わると帰ってゆかれる。
お客様のような神様だ。
ハナシを「印」に戻せなくなっているが、
松飾り、しめ縄、鏡餅の三つは一緒に作印したい。
というのはそういう想いから。
ROCAdesignさんがたくさんデザインして下さった中で、
もう少し簡素な感じ(松葉が少ない)のデザインを、
祈るような気持ちで12ミリ角にも彫刻してみたのが下の画像。
〔松飾り 12ミリ角と15ミリ角〕
きれいだー。
とてもきれいに彫刻できている。すごいぞ2号!
(彫刻機は2台ある。頼り切っている割には命名に愛がない)
が、
バランスを考えるとやっぱり15ミリ角かなとも思う。
しばらく遊びながら考えよう。
もう少しお待ちいただけると嬉しい。
充実の一日を
藤井あき乃